未鑑賞の方は、ネタバレなしの作品紹介記事をご覧ください。
どのあたりが現代日本的「家族映画」なのか?
『海よりもまだ深く』は紛れもなく「家族」をテーマにした映画です。そのような映画は多くあります。でも、より正確に言えばこの映画は「元家族」をテーマにしています。崩壊しそうな家族が再生していく物語というのはよくありますが(その中に名作もまた多くあります)、家族が最初から崩壊している、というのがこの映画のポイントでしょう。
元家族の中心にいるのは、というか、今や何の中心でもなくなってしまった男が、主人公の良多(阿部寛)です。周囲の人々にため息をつかれ、うだつの上がらない、ほとんどクズといってよいような彼の暮らしぶりがまず描かれます。そして、そんな暮らしの中でも彼が諦めきれないもの、慈しんでいるものが描かれます。それがすでに崩壊してしまった彼の家族、元妻の響子(真木よう子)と息子の真悟(吉澤太陽)です。
崩壊しかかった、あるいは崩壊した家族というものが物語に出てくると、どうしてもその先に「再生」というものが想像されます。でもこの映画で描かれたことに、その言葉はそぐわないでしょう。再生したのは家族ではなく、それぞれの心のあり方でした。すでに壊れてしまって、どうしても元に戻せないことがある。それでも生きていくために、かつて家族であった者同士がお互いを癒し合うことはできる。そしてそれぞれが、前を向いて歩いていく。そんなことが描かれていました。
もうひとつの伝統的「元家族」とは?
この物語には、もうひとつの「元家族」が登場します。それは、数ヶ月前に亡くなった良多の父、良多の母(樹木希林)、良多の姉(小林聡美)、そして良多という家族です。これは離婚などによる決定的な崩壊というより、子どもたちが独立したことによる緩やかな「解体」です(良多が独立しきれているかという点は微妙ですが)。でもその中にも、どうやら息子と同じくうだつがあがらなかったらしい父、父のようになりたくないと反目する(結局なってしまったのですが)息子、といった断絶があったようです。
このような「元家族」は、どちらかといえば伝統的に描かれてきたものです。それこそ、小津安二郎監督の世界的名作『東京物語』(1953)では、尾道の老いた両親と、独立して東京に出て行った子どもたちの間の断絶が描かれています。などと今更説明するのもおこがましいですが……。
『海よりもまだ深く』の「もうひとつの家族」では、そもそも父は亡くなってしまっており、家族自体が再生することはできません。でもたとえば、良多の中で壊れてしまった何かが回復していく様は描かれています。良多は、自分が小説家になったことを父が気にいらなかったのだと思っていました。でも、実は父はそれを心から喜び、買った本を近所に配って回っていたのだということを知ります。
この「元家族」は、決して不幸ではありません。料理は苦手ながらしっかり者の姉はしばしば母を訪ねているし、金に困って訪れる良多だって、軽口をたたきながらも結局は母のことを大切にしています。そして、この元家族の中心でそれを支えているのは間違いなく、良多の母です。
母(樹木希林)の裏腹な言葉
樹木希林だから当たり前という感じさえするのですが、良多の母はとにかく一挙手一投足が印象的と言ってよいほどの存在感を放っていました。彼女はまた、「どうして男は『今』を愛せないのか」などの印象的な言葉を多く口にしました。
この映画のタイトルを口にしたのも彼女です。良多との会話の中で彼女は、「海よりもまだ深く人を大切に思ったことなんかない」ということを口にします。つまり、この印象的なタイトル(テレサ・テン『別れの予感』からの引用と思われますが)はただ一度、否定形で語られるのです。でも、彼女はほんとうにこの言葉のままのことを、表面的な意味通りのことを思っていたのでしょうか。
彼女は「幸せってのはねえ、なにかを諦めないと手にできないもんなのよ」と言います。彼女のこの言葉の発し方は、軽やかでありながら重みのある、強烈に心に突き刺さるものでした。裏を返してこの言葉に秘められた意味を考えるなら、つまり「頑張って、辛さをこらえてまで諦めなければならないものがあるということは幸せなことだ」ということなのではないでしょうか。
つまり、彼女は「海よりもまだ深く人を大切に思ったことなんかない」のではなくて、そんな大切さが幸福に必ずしもつながっていかないという現実を受け入れて(諦めて)きたのでしょう。なぜなら、この言葉の意味を表面的にとらえるならば、明らかに嘘なのです。息子や娘への接し方、さらに蝶に重ねて死んだ夫を思い出した話を息子に聞かせる場面など、彼女は間違いなく自分の(元)家族を大切にし、愛しています。
彼女が「諦める」場面があります。息子の元妻に、やり直すことは不可能だと言われる場面です。彼女は、息子が幸せな家庭を築いていくことを心から願っていたのでしょう。それでも、あらゆる思いをぐっと飲み込み、何かきつい言葉を元妻に投げつけるようなことはせず、それどころか彼女のことをも慈しむような態度でそれを受け入れます。諦めるのです。だから「生きていける」、だから台風一過の美しい朝に家を後にする三人に対して、あのように手を振れるのです。
「ダメな阿部寛」はどのようにつくられたか?
阿部寛という俳優に長く不遇の時期があったことは、よく知られています。バブルの時代にモデル出身俳優として世に出た彼は、現在のような存在感ある俳優となるまでにかなりの雌伏期間を経てきました。その過程の中で、長身で彫りの深い二枚目という圧倒的な武器がむしろ足を引っ張ってしまった、ということが語られています。
今や彼は、二枚目はもちろん三枚目だとかダメ男、さらには古代ローマ人までも演じることのできる、幅の広さに定評がある俳優となりました。特に女性に愛想をつかされがちなダメ男という点では、ヒットドラマ「結婚できない男」での印象を強く残す方も多いでしょう。しかし筆者はこのドラマをほとんどちゃんと観ておらず、その意味で「阿部寛のダメ男」イメージをほぼゼロから組み立てねばなりませんでした。
阿部は良多として説得力のあるダメ演技をしていますし、他の登場人物もその輪郭をくっきりと描き出しています。しかしどうしようもなくあの顔立ち・上背が邪魔をして、映画の途中までは「ダメさ」がうまく馴染みませんでした。
彼のダメさを馴染ませてくれたのは、むしろダメな部分ではなく「優しさ」でした。ダメなくせに、家賃も養育費も払えないくせに母親を安心させようと小遣いを渡してしまう場面など、その「身の丈に合わなさ」が「ダメさ」を自然なものにしてくれたのです。
同時に、周囲の人物の優しさもまた重要でした。探偵としての部下である町田(池松壮亮)の存在は大きなものです。彼は最も近くで良多のダメさを目の当たりにしている人物です。金銭的に迷惑を被ってもいます。それでも、良多がそのダメさを発揮するとき、彼はしばしばヘラヘラと笑うのです。別にダメな人間を責めないことが優しさというわけではありません。ただ、彼のヘラヘラには何か、上っ面ではなく、良多の内なる優しさだとか哀しさを汲み取り踏まえた響きがありました。あの若さで密かに「わかっている」感じがまたよいのです。
宝くじは当たるのか?
息子の真悟が「宝くじが当たればまた家族一緒に暮らせるかな」ということを言います。突き刺さる言葉です。(元)家族が全員で、嵐の中散り散りになった宝くじを探す場面には、少しの滑稽さと、途方もない悲しさが混ざっています。
ややあからさますぎるメタファとも思えますが、ここでの宝くじとは「壊れてしまった家族のかけら」です。ですから、劇中で描かれることはありませんが、きっと宝くじは当たらないのでしょう。でも、皆で必死に探し集めることが大切なのです。「何かになれたかどうか」よりも、「何かになろうと思ってどのように生きたか」が大切なように。
ところで、劇中で描かれなかったこととしてもうひとつ「良多が賞を取った15年前の小説の内容」があります。どうやら家族の(特に姉にかかわる)プライベートな部分をモデルにしてしまったようで、姉に蒸し返されて責められていましたが、内容についての描写はそれだけです。元妻の新恋人(小澤征悦)も何かぬかしていましたが、あんな薄っぺらそうな男の感想は当てになりません。いや、本当に読んだかどうかも怪しいところです。
きっとその小説は、綺麗にまとまったものというよりも、「いろいろと穴はあるけれど一本強烈な芯の通った作品」だったのではないでしょうか。特に根拠もありませんが、なんとなくそんな気がします。そして、一作だけそのような作品を書けるのだがあとはからきしダメ、という小説家もよくいます。
「アレ」問題
この作品における良多の口癖は「アレ」です。適切な言葉がパッと思い浮かばなくて「アレ」で済ましてしまう、アレです。会話の中に出てくる「アレ」という言葉は、実は是枝作品においてけっこう目立つものです。確か「海街diary」でもそうでした。確かに私たちは、ほんとうにリアルな会話の中では無意識に「アレ」を多用します。関西のほうでは特に多い印象がありますが、とにかくリアリティを醸し出すという点では「アレ」は地味ながら強力な道具です。
ただ、曲がりなりにも小説家である、言葉に大きなこだわりを持つはずの良多が「アレ」を多用するところにはやや引っ掛かりがあります。母も、確か姉も「アレ」を使っていたので、なるほど(元)家族の共通言語的に使われているのだな、と納得していたのですが、探偵事務所の所長(リリー・フランキー)も使っているところを見てやや混乱してしまいました。このあたり、もう少し整理してくれてもよかったな……と思います。
蛇足(その他の下世話な話)
今回はもちろん、食事シーンのみ。難しいのは「カレーうどん」の扱いです。父の好物で、存命中(数ヶ月も前)から冷凍されていたカレーという点、それを受けて「男はすぐに賞味期限を気にする」というところも異常な説得力がありました。あの大切な嵐の夜の食卓、という点もポイントです。
しかしそれに匹敵するか、またはそれ以上なのは、母の作る「カルピスを凍らせたやつ」です。良多が買ってくる母の好物のプリン(だったでしょうか)の空き瓶らしきもので作っているところもよい。さらに、固すぎることが(子どもたちに食べてしまわれなくて)ちょうどいい、という点。世のバアさん方の、何か不便な点を「ちょうどいい」の一言で強引にメリットに変えてしまうあの生態は何なのでしょうね。圧倒的リアリティです。これ自体もたぶん薄くて(薄そうな感じに作っていました)、さほど美味しくないのでしょう。
というわけで、悩ましいところですが、今回のベスト食事シーンは「カルピスを凍らせたやつ」、固すぎるそれを親子揃って必死に砕く場面、で決定。
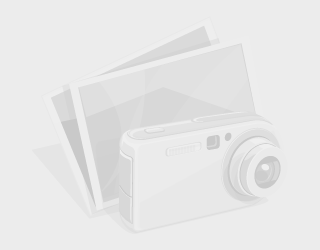
0 件のコメント :
コメントを投稿